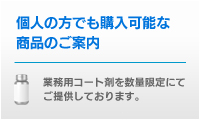太陽光発電のガラス表面に、簡単に安価に施工できる水性完全無機コート剤を既に開発済み。透過率/反射率の点でも太陽光を阻害しない製品です。
【絶対条件】
■紫外線劣化がしない
■透過度が落ちない
これが必須条件です。
透過率・反射率などの基礎データは既に実証済みですが、更なる商業化に向けたデータ取り及び当コート剤をご拡販して頂ける企業を求めています。
製品情報 -Products data-
目次
1.自動車コーティングあれこれ
1)自動車コーティングのプロとは?
自動車コーティングのプロとは、塗装表面に塗布されているアクリルのクリアーコート表面の傷消 しや下地調整に長けている技術者のことをいいます。彼らは、コート剤に関する化学的知見を有しているわけではありません。
コート剤の大まかな種類は、ワックス系(有機系)、フッ素系(有機系)、ガラス系(有機・無機ハイブリッド系/水性完全無機)の三種類に分類されます。特にガラス系と称しているコート剤は、Sio2(二酸化珪素)が含まれるものを指します。
コーティング技術者は、これらのコーティング材料メーカーあるいは販売業者の説明書あるいは指導に基づきコーティング技術を研鑽しており、その技術の高い技術者が「コーティングのプロ」と呼ばれます。
日本でコート剤開発を行っている企業はそれほど多くありません。特にガラス系と言われるハイブリッド系コート剤の多くはパーヒドロポリシラザン(SiNH)をベースとしており、原液をメーカーより購入し溶剤で希釈し自社ブランドとして販売しているものが多くあります。そのため、基本的な化学的知見がないままに販売しているメーカーの説明が、誤った知識としてコーティング業者に伝わり、それが一般化してしまうこともあります。
このような「一般的に言われるコーティングのプロ」は、本当のプロだといえるでしょうか?
3.ユーザーから自動車コート剤に求められる条件を全て満たしたCARPAL
| 求める条件 | CARPAL | |
|---|---|---|
| 条件のクリア | クリアのための性能 | |
| 無色透明である | OK | 微粒子シリカで完全透明 |
| 被膜表面で反射しない | OK | シリカの低屈折率で光の透過性良好 |
| 耐候性がある | OK | 完全無機質で、劣化・変色・退色しない |
| 薄膜である | OK | 50nm膜厚 |
| 防汚性 | OK | 水切れ性による自浄効果、易洗浄性(輪染み防止) |
| 伸縮追従性がある | OK | アンカー効果による超微細ポーラス構造被膜(1μm㎡に400~1000の針状SiO2が塗装塗膜の凹部に垂直方向に埋め込まれている状態で、三次元の被膜いわゆるシロキサンボンディングにはなっていない。(伸縮追従性) |
| 除去可能なこと | OK | 容易に除去可能 |
4.CARPALの特徴および他社製品に対しての優位性(徹底的なユーザー目線)
CARPALは、自動車コート剤の「容易にコーティング被膜を形成でき、塗装の保護および光沢の維持を目的とし、コーティング被膜が不要になった際には簡単に除去できるもの」という定義を満たした上で、環境への低負荷性、省資源性、安全性、易施工性に配慮し、自動車本体の塗装面を保護するための防汚・自浄効果・易洗浄性を付加しました。また、コート剤の本来の目的である塗装被膜の保護コート剤として、犠牲被膜的要素を持たせています。